
どこまで深いところで
ブランドパートナーと
繋がれるか。
マーケティング・コンサルタント
TOMOKI YASUHARA安原智樹
-
マーケティング
安原智樹
・コンサルタント - 1960年3月5日東京生まれ。マーケティング・コンサルタント。慶應義塾大学経済学部卒、専攻は計量経済学。消費財会社を中心にブランド・マーケティング、B2Bマーケティングの実務経験を15年近く積む。2000年に、企業内のマーケティング部門へのコンサルティングや、ブランディングの仕組み構築のコンサルティングを目的としたヤスハラ・マーケティング・オフィスを設立。講師として、日本能率協会(2002年~2009年)、立命館アジア太平洋大学 (2003年~2011年)でマーケティングや消費者行動論を教える。『入門ブランド・マーケティング』(プレジデント社)、『マーケティングの基本』、『ブランディングの基本』(日本実業出版社)など、著書多数。2015年より、東京世田谷より信州松本に移住し活動、現在に至る。
情報をコントロールできない時代と、
だからこそのブランディングとは。
ネットが台頭するまでは、情報をコントロールするということが可能でした。コントロールというのは言い過ぎかもしれません。しかし、一部の大手と呼ばれる企業がテレビに代表される限られたメディアを利用して、企業側が加工済みの情報を一方的に発信する時代は2000年ぐらいまでは、普通でした。これをマス・マーケティングと呼ぶわけですが、大手の広告代理店が自由に情報を扱うことができた送り手と受け手に情報格差があった時代でもあります。さて、これがネットの普及によって情報の非対称性が崩れ、受発信が生産者と消費者で対等になったのです。当然ながら、生活者も情報を持っているだけでなく、企業側が想定しない情報を発信したりするようになったわけです。たとえば、メントスコーラのように、コーラの中にソフトキャンディ「メントス」を入れると勢いよく噴射するという現象は、一般の投稿から一気に広がり拡散しました。そして、想定外の消費が起きる。某回転寿しの社員がふざけた動画をアップすれば、それはたちまち不祥事として多くの人が目にするところとなりました。そして、想定外の売り上げダウンが起きる。個人が手作りの音楽とダンスで情報発信すると、世界的な有名人がそれを面白がってSNSで紹介する。そして、昨日まで完全にノーマークだったピコ太郎が日本を代表するエンターティナーになる。すべての人々が情報を待つ側から、発信する側に回った。ブランディングはこういった全員が受発信に関して対等な時代に語られるものとなったのです。
誤認も曲解も受け入れて成り立つブランディング
ブランドとはなんでしょうか? 商品とはどうちがうのでしょうか? まず、商品は市場の中に存在した時、商品と呼べます。でも、まだブランドではありません。ブランドとは受け手の消費者の頭の中に存在している状態を意味します。人の頭の中ですよ、そもそもコントロールなんかできないですよね。ただ、昔は大量の広告で強制的に頭の中にブランドを存在させようという荒技がマス・マーケティングという名の元に行われていたわけです。
さて、あなたが聞いたそれは、正しいニュースか、フェイクニュースか。ご承知の通り、今はその選別すら難しい。誤った情報をそのまま信じて、消費者がブランドのイメージを誤認することも、十分にありうるのです。たとえば、多くの人が利用するグルメサイトで、評価の低い口コミが、店名の記憶を間違ったままの書き込みだったり、来店した日が土砂降りで、その気分で点数を減らすなんていうのは、もう驚かないですよね。そういった誤認は、飲食店だけでなく、今や日常茶飯事です。つまり誤った情報を是正したり、不利な情報を削除したりすることができない前提で、ブランドを考えていかないといけない。もちろん、良い誤解だってあります。メントスコーラのような偏愛さえ、あり得るのですから。僕が悩むのは、このなんでもありの世界で、発信側の企業は何ができるのだろうっていう疑問です。ブランディングってスカッと爽やかな存在じゃないとしたら、何なんだろう?受信側の頭の中のどれが正しいとか、どれが誤認なのか、フェイクの一人歩きをどうするのか、なんて扱いきれないでしょう。で、そういう前提を全肯定してみたとき、これからのブランディングに欠かせないのは、ブランドパートナーの存在だと僕は考えています。ブランドパートナーとは、ブランドと一蓮托生の存在。誤解を恐れずに言えば「一緒に心中してください」とブランド側がお願いできてしまえるような関係性。どこまで深いところでブランドパートナーと繋がれるか。それがこれからのテーマになると思います。
ブランドパートナーとは何者か。
マーケティングの世界では以前、ブランドパートナーのような存在のことを、コアターゲットと呼んでいました。ターゲットというのは、標的という意味。戦略という文字にも「戦」という字が入っているように、マーケティング用語は、ほとんどが戦争用語なのです。果たしてこの言葉が、ふさわしいのかどうか。疑問を感じるようになって、僕自身はコアターゲットではなく、ブランドパートナーと呼ぶようになりました。そして、この辺りが、マーケティングとブランディングの分岐点とも呼べるところではないかと。戦いが始まった瞬間から、相手との駆け引きが生まれる。そういう駆け引きがあっては、本当の信頼関係を築くことはできないでしょう。おまけに、何やら一方的な強制感さえ感じられますよね。そう、テーブルを挟んで向かい合う関係から、同じサイドで席を並べて同じ風景を眺める仲を目指しましょうという姿勢です。単に商品を購入してくれるお客様という位置付けではなく、ブランドを応援してくれる真の仲間であり、企業から見ても一緒に長くお付き合いしたい顧客なのです。それをブランド・パートナーと呼ぼうという提案です。この人たちの生活と深いところで分かち合い、この人たちと共に生きていく。そんな覚悟がブランド側にも必要になります。だって、同じ風景を見たい訳ですからね。ブランドが抱く志に共鳴してくれる、同志のような存在とも言えるでしょう。だからこそ、大事になるのはブランドの志の部分なのです。志がお互いのブランドを眺める視点をぶれないようにしてくれるのです。パラドックスが考えている志ブランディングは、そういった意味で非常に時流にあっている。むしろ僕は一歩二歩先をいっているようにも感じています。
「差別化」から「差積化」へ。
今、企業の佇まいや姿勢が問われています。ブランドと顧客が対等になればなるほど、その傾向は強まるでしょう。ですから、ブランディングも日々の研鑽が問われるようになっています。商品そのものを魅力的に見せる、といった表面的なブランディングではなく、売り場の店員や、その企業の従業員、ブランドの価値をつくる一人ひとりの人間のふるまいから始まって、経営者の生き様まで、すべての立ち振る舞いが重要なのです。お客様は賢いから、ブランドの違和感を言葉にできなくても、「匂い」でわかる。挨拶のぎこちなさや、トラブルがあった時の対応で見せる素の表情ひとつ。とっさのリアクションや空気感は、お客様にブランドの印象として深く残ります。行動を規定するためのマニュアルをつくればいいという問題でもありません。もう、とっさですから、コントロールなんかできないですよね。お里が知れる部分もまたブランディングの一部なのです。望むと望まずに関わらず。すると、心から従業員が、ブランドの理念に共感して、体現しているか。お客様は、そこを見抜きます・・・嗅ぎ分けるといったほうが正しいと思います。情報をコントロールできていた時代と比べて、発信側にとっては怖い時代です。ただ、もうマーケティング経費の多寡ではなくなっているのは朗報でもあります。特に、規模で勝負してない企業にとっては追い風ですからね。大企業の看板で押し切ろうとする古いタイプにとって辛い時代というのが、より的を得た意味合いではないでしょうか。
情報をコントロールできる時代に通用していた「差別化」も、マーケティング手法の鉄板でした。しかし、今は難しくなってきています。グローバル化で、同じようなバリューを提供している企業が世界のどこかに存在し、あっという間に模倣され模倣し返すという現象が増えたことも一因です。「差別化」は商品にしろ、サービスにしろ、発売当初に訴求するものです。この「差」の埋まるスピードが速くなって、もはや、大量広告で投資を回収する前に失速することが多くなっているのが、企業側の悩みになってきているわけです。代わりに僕が提唱しているのは「差積化」という考え方。差積化というのは、少しずつ少しずつ積み重ねて継続していくことで生まれる違いのこと。ブランドをテーマに語るコンテンツだったり、ブランドの愛好者とのコミュニティだったり、形式は多種多様です。まったく同じところからスタートしても、10年20年と続けていくうちに、溜まっていくコンテンツや顧客とのより良い関係がブランドを全然違うところに連れて行ってくれる。もう、競合が真似しようとしても真似するのが億劫になるくらいの世界にたどり着いてしまっている、そんな、普段の構え、姿勢、日々の継続がものをいう世界を「差積化」という言葉で目指したらどうかと、そう提唱しています。特に、情報の差積化というのは、かつては自分たちでメディアを確保できるような、お金持ちにしかできなかった。でもネットがあれば、大きい会社も小さい会社も関係なく自分たちで情報を継続的に発信できる。お金をかけなくても、明日からでも、「差積化」は始められるのです。よその会社と差別化ができないと頭を抱えている会社は発想を180度転換して、ぜひ「差積化」を続けて欲しいと思います。
「何を買いたいか」ではなく
「何を信じたいか」。
ブランディングを語る上で、もうひとつ触れておきたい重要なポイントは、物語があるかどうか。そして、物語を信じたくなるかどうかです。人間は腑に落ちるストーリーがないと、自分自身を説得できない生き物なんです。あれこれメリットを言われても、そこに物語がなければ、他にもっといい品物があったんじゃないかと、買った後も人の気持ちは揺らいでしまう。認知的不協和って呼ばれる現象です。100円の商品であろうが、100万円の商品であろうが、「100%正解の購入だった!」と断言できるものはないのです。99%ぐらいはあってもね。1%は「もしかしたら、あれもよかったんじゃなかったかな?」なんて心の奥底で疼くわけです。まあ、100円だったら、「まあいいか」ってすぐにスルーしてしまうけど、リピートするかどうかの時に響いてきます。けれども「自分たちはこういう気持ちで、こういうことを目指して、こんなものづくりをしている。それが本当にいいと思ったら買ってくださいね」と語られたら、買った人はその言葉を信じる。いや、信じたい、そういう気分の良さを感じてくれたりします。そうなれば、もう揺らがないんです。今の購入への疑いが少ないことは価値なんです。こういうことを「ブランド・ストーリー」と僕は呼んでいます。そう、物語とは、自分の選択に意味があったと心から信じられる意味の組み立てで、人は対価を払うようになってきていると思います。「何を買いたいか」ではなく「何を信じたいか」。そういう価値観で捉えると分かりやすいかもしれません。
物語は、ブランドとブランドパートナーとを結びつけるだけではありません。物語があることは、ブランド側にとっても心の支えになり、自信になる。お客様に「うちの商品の魅力はここです」とご説明したとき、もし「もっと安く似たような商品が他にもあるよ」と言われたら、たじろいでしまうかもしれない。でも、自分たちにしか語れない物語があれば、揺らぐことはないのです。その社員の立ち振る舞いに、消費者はブランドの匂いを感じるのです。ですから、聴きたくなる、語りたくなるブランド・ストーリーをつくることが、受信者側だけでなく発信者側にとってもブランディングの肝になっています。いいモノをつくるから、とにかくモノを見て判断して欲しい、という寡黙な職人スタイルだけでは仕事が完了したとは言えないのです。どんなに権威のある刀職人であっても、竹細工職人であっても、提供するモノの価値を言語化して説明したり、ワークショップのような人々に価値の源泉である技を見せる場に出て行くことが求められているのではないでしょうか。当然のことながら、工場や研究所、バックヤードでサポートする社員さえ価値の一部を担っている尊い存在だと胸を張れるようなブランドであることが大前提ということでもあります。ブランディングが意味するものは、「すべての活動がひとつの物語に織り込まれ」、「すべての社員がひとつの価値を担っている」ことを世間に見えるようにする、もし、望まれたなら体感できるようにすること、そう僕は捉えています。

SUPPORTERS
サポーターズ
-
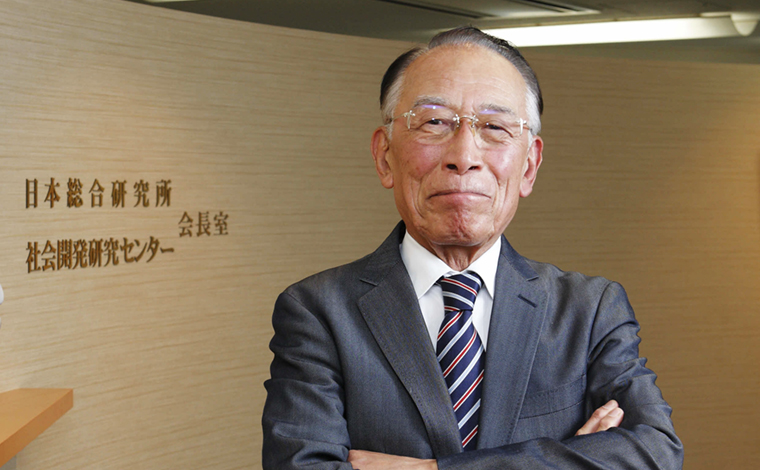
「夢」と「志」は違う。
「夢」を追う程度の人間になるな。MESSAGE From野田一夫 氏
-

流行に流される人が多い世の中だからこそ、
本質を言葉にできる力に価値がある。MESSAGE From楠木建 氏
-

会社とは、関わるすべての人たちが幸せに
なるためにある。
そんな当たり前のことを
ちゃんと当たり前にしたいんです。MESSAGE From坂本光司 氏
-

マーケティングから、アートの時代へ。
語られるべきは、自分たちのストーリー。
本気で何をしたいか、という思いなんです。MESSAGE From山口周 氏
-

志を「しょせんは綺麗ごと」という人もいます。
しかし、「綺麗ごと」を貫いた会社は強い。
それもまた、まぎれもない事実です。MESSAGE From河合太介 氏
-

300年以上続く長寿企業。
その志を伝えるメカニズムとは。MESSAGE From田久保善彦 氏
-

どこまで深いところで
ブランドパートナーと繋がれるか。MESSAGE From安原智樹 氏




